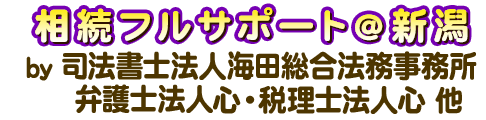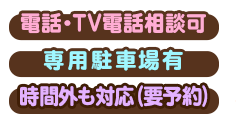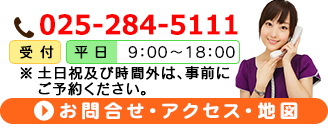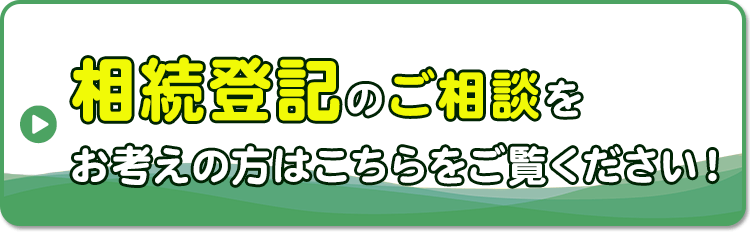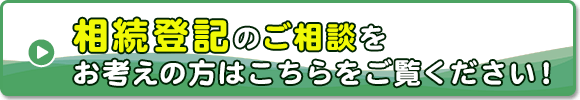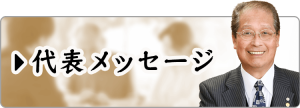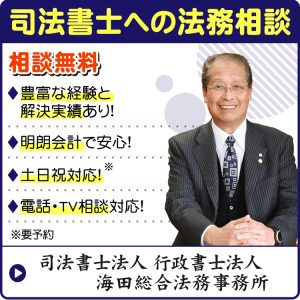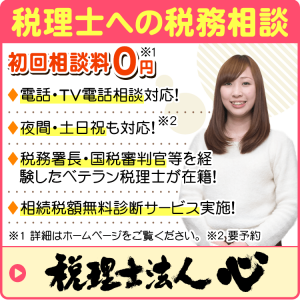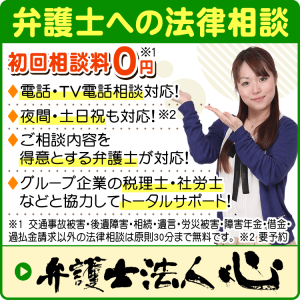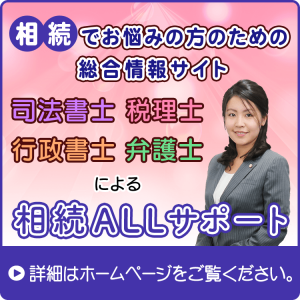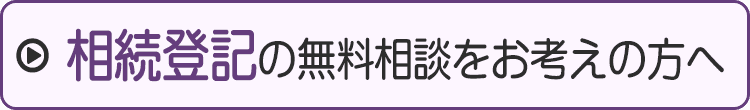不動産の相続手続きの期限
1 相続したことを知ったときから3年以内に所有権移転登記を行う必要がある 2 令和6年4月1日より前に相続していた場合は、令和9年3月31日が期限 3 遺言書がなく、遺産分割が期限内に成立しない場合の期限
1 相続したことを知ったときから3年以内に所有権移転登記を行う必要がある
令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に遺産分割協議又は遺言書の内容に基づいて相続登記(所有権移転登記)の申請をその不動産の所在地を管轄する法務局でしなければならないこととなりました。
参考リンク:新潟法務局・相続登記が義務化されました
特に正当な理由なく、期間内に手続きをしない場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
2 令和6年4月1日より前に相続していた場合は、令和9年3月31日が期限
令和6年4月1日から始まった制度ですが、それより前に不動産を相続して、未だ相続登記を行っていない場合にもこの義務は適用されます。
具体的には、猶予期間として定められた、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
「過去に不動産を相続したような気がするが、どこにある土地を相続したか分からない」という方もいらっしゃると思います。
そのような場合は、被相続人(亡くなった方)が保管していた権利書、被相続人宛に届く小手資産税課税通知書又は被相続人が不動産を持っていたと思われる所在地の市区町村に対し、被相続人の相続人名義不動産に関する「名寄帳」を取得することで把握することができます。
参考リンク:新潟市・固定資産課税台帳(名寄帳)交付申請
また、令和8年2月2日から運用が始まる「所有不動産記録証明書」によって、相続した不動産の有無やどれだけあるかについて「法務大臣の指定する登記所」において、把握できるようになります。
具体的な運用内容は不明ですが、これにより、権利書が紛失していた場合や、課税明細書に乗らない非課税の土地、所在場所が分からず名寄帳の請求先が分からなかった不動産について把握することができるようになります。
期限が限られている中で、調査を行う上で、重要な制度になりますので、今後どのように運用されていくか期待されています。
参考リンク:法務省・所有不動産記録証明制度
3 遺言書がなく、遺産分割が期限内に成立しない場合の期限
遺言書がなく、遺産分割協議がまとまりそうになく、遺産分割協議に基づく相続登記が期限内に行えない場合は、「相続人申告登記」という別の登記を行う必要があります。
権利移転の効果はなく、あくまで相続人であることを登記するものですが、各相続人が単独で申出を行うことが可能です。
この相続人申告登記については、不動産の相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
その上で、相続人申告登記後に遺産分割がまとまった場合には、遺産分割の結果に基づく相続登記を遺産分割の日から3年以内に行う必要があります。
参考リンク:法務省・相続人申告登記について